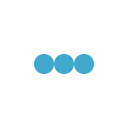菊地牧場様(栃木県那須塩原市)

■飼養頭数:71頭(搾乳牛:47頭・育成牛:24頭)
■労働人数:2名
■1号機稼働年度:2001年4月
■2号機入替年度:2012年11月
導入を決めた2年後の4月にロボットが稼働したんですが、稼働と同じ年の12月に主人が他界しました。
なぜ、主人がこんなに強くロボットを望んだかというと、実は私は20歳の時に怪我をして膝が悪くて。
"「膝が悪い状態で搾乳を続けるのは、負担が大きい。これからずっと酪農を続けていくなら、搾乳ロボットが1番だ」と言って、奥さんのために、ご主人は搾乳ロボットを考えていたんですよ"と、主人が亡くなってから、酪農協の方に聞きました。
その時に、「私のために入れてくれたロボットだったら、私がちゃんと主人の想いを継いで、酪農を続けていくしかない」と、
迷わずに、そのまま酪農を続けることができました。
ロボットでなければ、10年以上、1人で酪農をやっていくのは無理ですし、ロボットがいてくれたお陰で続けてこれたという想いは大きいですね。ロボットは、今も、私の片腕で働いてくれています。
娘が牛舎清掃や牛の観察、ロボットのセルフメンテナンス、訪問回数の少ない牛の追い込みを行って、私が飼養管理ソフトT4Cを使って朝晩2回の牛データの確認、育成牛の給餌や哺乳を担当しています。
ロボットの訪問回数が少なくて追い込みが必要な牛は、現在は1頭いるかいないか・・・くらいですね。
牛を観察する時間が取れるので、コンディションを気にして見ています。痩せたり、太り気味の牛は注意して観察して、ロボットが給与する餌を自動から手動に切り替えて内容を調整したり、乾乳中に長めの粗飼料を食べさせたりしています。
現在、1頭当り1日平均で2.9〜3回を搾乳していて、多い牛では4回搾っているので、乳量が出る分、脂肪分が少なくなるのが悩みですね。今年の夏は分娩がピークを迎えるので、その前にロボットで給餌する濃厚飼料での調整を考えています。

とても使いやすいです。
発情すると、活動量のデータは上昇して、反芻時間のデータは下がって、綺麗な三角形のグラフを描くので、発情が見事にわかります。
また、乳量が下がっている牛は、反芻時間や体重も落ちてくるので、体調の管理や乳房炎の発見に、とても役立っています。繁殖状況や育成牛も登録して、牛群台帳として活用しています。
私が1人で10年以上やってこれたのだから、出来ると思います。
導入当初、人間よりも、牛の方がロボットに慣れるのは早かったので、牛はとても順応性が高いと思います。ロボットを信じて、牛にも順応性があることを信じることが、大切だと思います。
(瞳様)主人は「牛の立場に立った牛飼い」を目指していましたが、それを実現できる放牧での飼養を行いたいということが、私たち母娘の長年の夢です。ロボット導入のタイミングで放牧を始めたくて、周囲の人とも色々と検討した結果、見送ることにはなってしまいましたが、いずれは、"牛の背に光が当って、自然に草をはみ、広い場所を自由に駆け回ることができる"ロボット搾乳での放牧の夢を母娘で一緒に叶えたいです。
農場経営は、2人で一緒に上手く作業をこなしながら、やっていきたいですね。これまでは私1人で細々とやっていましたが、娘が経営に加わってくれたので、思い切って頭数を少しずつ増やしている状況です。
(若菜様)これからは、経営を良くしたり、牛をもっといい環境で育てることを考えていきたいです。今は、牛についてもっと勉強しなければと感じています。
いずれは、牛舎の離れで、昼間はカフェ、夜はバーになるお店を開いてみたいですね。衛生責任者の資格を取ったので、自家製チーズ作りにもゆくゆくはチャレンジしてみたいです。

※(左)菊地若菜様 (中央)栃木支店 支店長 高久博光 (右)菊地瞳様