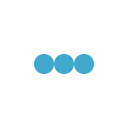株式会社キリシマ農場様


アメリカンベストサービス株式会社
代表取締役 中村良久様
株式会社キリシマ農場
中村良史様(写真左)
川越進一様(写真右)
先行して2台のロボットの稼動を始めたキリシマ農場様。
搾乳ロボット牛群の管理を担当されているお2人にお話を伺いました。
「夏は昼間が暑いので、牛のロボット訪問は朝と夕方が多くなります。暑くなるまで乳量の平均は40kg位でしたが、暑くて食い込み量が下がると、乳量も35~36kg位まで下がりました。搾乳回数は平均3.6回を維持しています」
T4C(飼養管理ソフトウエア)のシステムはいいと思います。1回目の乳検が終わったので、これから乳脂肪もチェック※していきます。
※初期値となる乳検データを登録すると、乳脂肪と乳タンパクを搾乳ロボットで計測できます。
乳牛の繁殖管理は、和牛の受精卵の移植がメインです。PGで排卵を誘発して黄体を確認し、すぐ人工授精します。
発情に関するデータは、移植1週間後に、着床したかどうか判断するための参考にしています。
実は、搾乳ロボットの導入を反対していた中村良史様。
「以前はパーラーで搾っていたので、ロボットは必要ない、と考えていましたが、実際に導入してみると、総合的にはエクセレント。
他の人にも色々話を聞きましたが、LELYだからいい。正直、ここまでやってくれるとは思いませんでした。すごく進歩していると思います」
特に、個体の細かな部分がデータで見られ、1分房ずつ健康状態がわかることや、牛の体調管理に役立つ乳温の測定機能に、ご満足されています。
ただ、中村様は、導入当初、心配でロボットから離れられず、少しでも訪問時間が空くと、すぐに牛をロボットに追い込んでいたそう。
神経質になってロボットに付きっ切りになり、体を壊したことをきっかけに、思い切って牛を放っておくことに。
「そうしたら、順調に牛がロボットに入って、なんて楽なんだと。ロボットに任せるのが1番だとわかりました」
「まずは、ロボット2台で120頭の搾乳を目安にします。
当農場では、和牛の繁殖をしていることもあって、乳牛の頭数には固執していません。
頭数を増やすより、搾乳回数を増やして、効率よく生産乳量を増やしていきたいですね」